2017/06/05
意外と知らない!? 正しい残業代の計算方法(弁護士執筆)
執筆者 編集部弁護士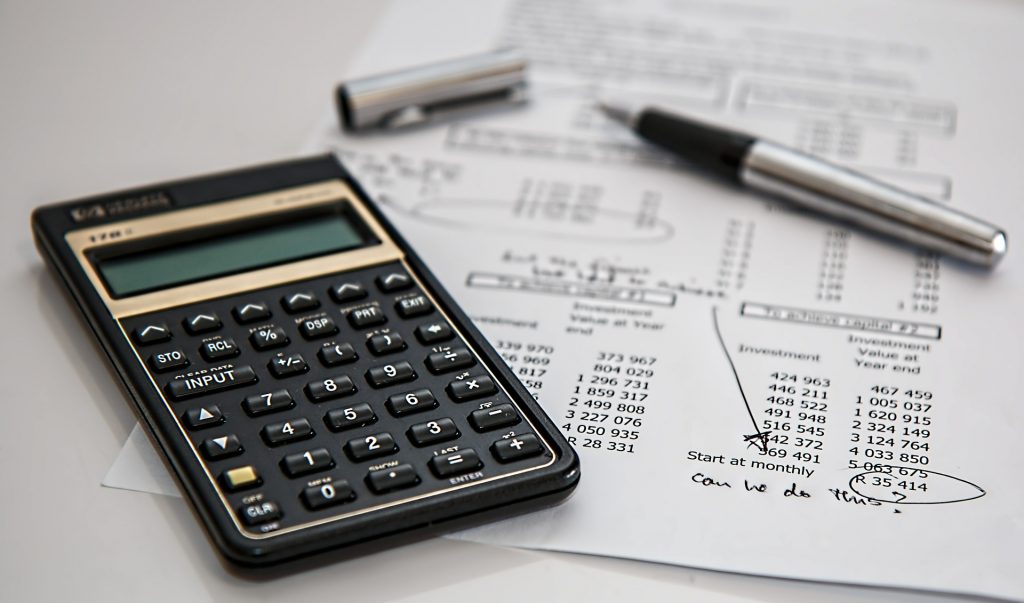
残業した場合には、会社から残業代・残業手当が支払われます。そして、会社から支払われた残業代・残業手当が、法律上の残業代よりも少ない場合には、会社に対して差額を請求できます。
しかし、法律上の残業代をどのように計算すれば良いかについては、意外と正しく知られていないのではないでしょうか。
そこで今回は、残業代の計算方法について解説します。
1.通常の勤務体系の場合
残業代は、
という式で計算します。
「残業時間」「1時間当たりの基礎賃金」「割増率」については、これから詳しく説明します。
(変形労働時間制やフレックスタイム制の方は、2.や3.をご覧ください。)
1-1. 残業時間
残業代を計算するには、まずは残業時間がどれくらいかを知る必要があります。(なお、裁判における残業時間の認定方法の詳細については、「実は重要!?裁判における残業時間の認定方法 (弁護士執筆)」をご参照ください。)
1-1-1. 残業時間=「所定労働時間を超える労働時間」
「残業時間」は、「所定労働時間」を超える労働時間です。
毎日同じ定時で働いている場合や、定時が日ごとに違ってもシフト制で勤務している場合には、会社との雇用契約や就業規則で、1日あたり何時間働くか(定時など)、1週間あたり何時間働くかという「所定労働時間(しょていろどうじかん)」が決められているはずです
この所定労働時間を超えて働いた時間が、残業時間となります。
1-1-2. 所定労働時間には法律上の上限がある
この所定労働時間ですが、会社がどれだけ長く決めてもいいというわけではありません。労働基準法(労基法)により、所定労働時間は、1日8時間、1週間で合計40時間までとすることが決まっています。この1日8時間、1週間で合計40時間の労働時間を「法定労働時間(ほうていろうどうじかん)」といいます。
法定労働時間より長い所定労働時間が就業規則などで決まっているとしても、労基法によって無効となります。そしてこの場合、1日8時間、1週間で合計40時間の法定労働時間を超えて働いた部分が、全て残業時間となります。
ただし、小売業等の小規模な事業場では、法定労働時間が1週間で合計40時間ではなく、1週間で合計44時間となる例外もありますので、ご注意ください。(これからの説明で「1週間で合計40時間」としている部分についても、基本的に同じです。)
1-1-3. 休日労働の場合
労基法は、1週間に1日(または4週間に4日)の休日を労働者に与えなければならないと定めています。この規定によって労働者に与えられた休日を「法定休日(ほうていきゅうじつ)」といいます。法定休日に働いた時間は、長くても短くても、その全てが残業時間となります。
例えば、休日が週1日の方の場合、その日が法定休日です。
土日休みなど、週休2日以上の契約で働いている方も多いと思います。この場合、就業規則などで、どの曜日が法定休日かが決まっていれば、その曜日が法定休日になります。
どの曜日が法定休日かが決まっていない場合は、休みの曜日のどちらかが法定休日になります。
(どの曜日が法定休日になるかは法律上の解釈によって決まるのですが、法律で確固たる決まりがあるわけではありません。例えば、土日休みの場合も、土曜日を法定休日とする行政解釈がある一方で、日曜日を法定休日とする裁判例もあります。)
法定休日以外の休日における労働は、通常の勤務日における労働と同様に扱われます。
1-1-4. 36協定違反との関係
会社が法定労働時間を超える残業や法定休日の残業をさせるには、原則として36協定(さぶろくきょうてい)が締結されていることが必要です。36協定では、1か月あたり45時間以内といったように、残業時間の上限が決まっています。
この36協定の残業時間の上限は、残業代の計算とは関係がありません。つまり、36協定の上限以上に残業させられたという場合であっても、36協定の上限に関係なく、実際に労働した時間をもとに残業時間と残業代を計算します。
1-2. 1時間あたりの基礎賃金の計算
でした。
次は、1時間あたりの基礎賃金の計算方法です。
「1時間あたりの基礎賃金」は、残業1時間につき、基本的に何円もらえるかという金額のことです。いわば「時給」のようなものです。
1時間あたりの基礎賃金は、普段の給料から決まる「基礎賃金(きそちんぎん)」の額を、1時間あたりに割って、計算します。
具体的な計算の仕方については、これから説明します。
1-2-1. 基礎賃金には、基本給と一部の手当てが含まれる
基礎賃金は、普段もらっている給料の額によって決まります。ただし、一部の手当・ボーナスなどは、普段の給料の額から差し引かなければなりません。差し引かれる手当・ボーナスなどは、次のとおりです。
| 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等) |
| 通勤手当 |
| 住宅手当 |
| 家族手当 |
| 別居手当 |
| 子女教育手当 |
| 臨時に支払われた賃金 |
もっとも、各種手当やボーナスという名前なら必ず基礎賃金から差し引かれるわけではありません。基礎賃金から除かれるためには、現実に各種手当やボーナスとしての実態がある必要があります。実質的な基本給が家族手当などに付け替えられても、残業代の金額が減ることはありません。
1-2-2. 基礎賃金の具体的な計算方法
基礎賃金の金額が把握できたら、次は、1時間あたりの基礎賃金を計算します。
月給制の場合は、月の基礎賃金の額を、就業規則などで決まっている1か月間の労働時間(所定労働時間)で割ります。
ただし、月によって日数や土日の数が違いますから、1か月間の所定労働時間は毎月違うのが通常です。この場合、1か月間の所定労働時間を、1年間の平均から求めます。
月給24万6000円、就業規則上は1日8時間労働で土日祝日、年始(1月3日まで)、年末(12月29日以降)が休みの場合を考えてみます。
2017年の1年間の勤務日数は246日(休みが119日)で、1年間の所定労働時間(就業規則上の労働時間)は、
8時間×246日=1968時間
となります。
したがって、1か月の所定労働時間は、
1968時間÷12か月=164時間
となり、1時間あたりの基礎賃金は、
24万6000円÷164時間=1500円
となります。
年俸制の場合も、月給制の場合と同様、年俸の金額を就業規則などで決まっている1年間の労働時間(所定労働時間)で割って、1時間あたりの基礎賃金を求めます。年俸制だから残業代を請求できないということはありません。
1-3. 残業代の割増率
でした。
次は、割増率です。
割増率(わりましりつ)は、法定労働時間(1日8時間、1週間で合計40時間)を超えた残業かどうか、深夜(午後10時から午前5時まで)の残業かどうか、法定休日の残業かどうかによって、異なる率が定められています。
1-3-1. 法定の時間を超える残業の場合
実際の労働時間が法定労働時間(1日8時間、1週間で合計40時間)を超えた場合、その法定労働時間外の残業については、割増率を1.25倍として残業代を計算します。
1時間あたりの基礎賃金が1500円の人が、月曜日に8時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に10時間、金曜日に9時間、土曜日に2時間働いた場合を考えてみます。
所定労働時間は1日8時間、1週間で合計40時間(法定労働時間と同じ)とします。また、法定休日は日曜日とします。
この場合、火曜日の1時間分、木曜日の2時間分、金曜日の1時間分が、1日8時間の法定労働時間の上限を超えます。また、土曜日の2時間分も、1週間で合計40時間の法定労働時間の上限を超えます。
したがって、これらの合計6時間が残業時間となり、この残業は法定労働時間外のものとなります。
したがって、この週の残業代は、
1500円×6時間×1.25=1万1250円
となります。
この法定労働時間外の残業が、深夜(午後10時から午前5時まで)である場合には、割増率を1.25倍ではなく1.5倍として、残業代を計算します。
1-3-2. 法定の時間を月60時間以上超える残業の場合
中小企業ではない大企業では、法定休日以外の実際の労働時間が法定労働時間を1か月あたり60時間以上超えた場合、その60時間を超えた部分の残業については、割増率が高くなります。
この場合、1か月あたり60時間を超える部分の割増率は1.5倍として計算します。深夜残業にも該当する場合には、割増率を1.75倍として計算します。
1時間あたりの基礎賃金が1500円の人が、法定労働時間が160時間の月に、法定休日以外で265時間働いた場合を考えてみます。所定労働時間は法定労働時間と同じであるとします。
この場合、残業時間は、
265時間-160時間=115時間
です。これは60時間を超えているため、
115時間-60時間=55時間
の部分については、割増率が1.5倍になります。
したがって、残業代は、
1500円×60時間×1.25=11万2500円(60時間以下の部分)
1500円×55時間×1.5=12万3750円(60時間を超える部分)
→11万2500円+12万3750円=23万6250円(合計)
となります。
この割増率の加算は、今のところ中小企業ではない大企業だけが対象です。中小企業では、残業時間が法定労働時間を1か月あたり60時間以上超えたとしても、割増率は1.25倍(深夜残業でもある場合は1.5倍)で変わりません。
割増率が変わらない中小企業は、以下の条件に該当する企業です。
| 小売業 | 資本金5000万円以下、または、常時使用する労働者50人以下 |
| サービス業 | 資本金5000万円以下、または、常時使用する労働者100人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下、または、常時使用する労働者100人以下 |
| その他の事業 | 資本金3億円以下、または、常時使用する労働者300人以下 |
1-3-3. 休日労働の場合
休日に働いた場合は、その休日が法定休日かどうかによって、割増率が異なります。
法定休日に働いた時間は全て残業時間になります。
法定休日に残業した場合、残業時間に1時間あたりの基礎賃金を掛けて、その上さらに1.35倍の割増率を掛けて、残業代を計算します。
深夜残業にも該当する場合は、割増率を1.35倍ではなく1.6倍として、残業代を計算します。
法定休日以外の休日に残業した場合は、この割増率の対象ではなく、通常の勤務日における残業の場合と同じです。
1-3-4. 就業規則などに割増率の定めがある場合
ここまでで説明してきた割増率は、雇用契約や就業規則に割増率の決まりがない場合の法定の割増率です。
もし雇用契約や就業規則で、法定の割増率より高い割増率が決まっていれば、雇用契約や就業規則で定めた割増率が適用されることになります。
他方で、雇用契約や就業規則に、割増率を法定の割増率未満にすると書いてあったとしても、それは労基法によって無効になります。この場合、法定の割増率で残業代が計算されることになります。
1-3-5. 法定の時間内の残業の場合
所定労働時間は、会社との雇用契約や就業規則で決まります。この所定労働時間は、1日8時間、1週間で合計40時間の法定労働時間より短く定められている場合があります。パート勤務などを想像してもらえば、イメージが湧きやすいかと思います。
このような場合、所定労働時間分は超えているが、法定労働時間は超えていない残業が発生しうることになります。例えば、週に20時間働く契約にもかかわらず、週に30時間働いたような場合です。このような法定労働時間の範囲内で所定労働時間分を超えた残業のことを、「法定内残業(ほうていないざんぎょう)」といいます。
法定内残業の残業代については、雇用契約や就業規則に決まりがあることもあります。この場合、基本的にはその規定に基づいて残業代を計算します。
これに対して、法定内残業の取り扱いが雇用契約や就業規則に書いていない場合もあります。この場合には、法定労働時間を超えた残業とは異なり、法定内残業の場合は1.25倍の割増率を掛けることはありません。単純に、残業時間に1時間あたりの基礎賃金を掛けて、残業代を計算します。
1時間あたりの基礎賃金が1500円で、土日休みの週休2日、所定労働時間が1日7時間の人を例にとって考えてみます。
この人が、月曜日に8時間、火曜日に7時間、水曜日に7時間、木曜日に10時間、金曜日に8時間、働いたとします。
この場合、木曜日の2時間分は法定労働時間(1日あたり8時間)を超えます。他方で、月曜日の1時間分、木曜日の1時間分、金曜日の1時間分については、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間(1日あたり8時間、1週間あたり40時間)の範囲内です。
したがって、この場合、法定労働時間外の残業が2時間、法定内残業が3時間となるため、この週の残業代は、
1500円×2時間×1.25=3750円(法定労働時間外の残業)
1500円×3時間=4500円(法定内残業)
→3750円+4500円=8250円(合計)
となります。
法定内残業であっても、深夜残業に該当する場合には、1.25倍の割増率を掛けて、残業代を計算します。
2.変形労働時間制の場合
ここまでは、毎日同じ定時で働いている場合や、定時が日ごとに違ってもシフト制で勤務している場合といった、典型的な働き方の場合を前提に説明してきました。
次は、変形労働時間制の場合について説明します。
2-1. 変形労働時間制とは
「変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)」は、ある期間については短時間だけ働く代わりに、別の期間には1日8時間以上または1週間で合計40時間以上働くといったような制度です。
変形労働時間制では、短時間だけ働く期間と長時間働く期間をまとめて、1セットの期間と考えます。
変形労働時間制では、就業規則などで、どの期間を1セットの期間とするかが決められています。また、その1セットの期間に何時間働くかという労働時間数も決められています。
この労働時間数には上限があり、法定労働時間の総枠を超えてはなりません。法定労働時間の総枠は、40時間×清算期間(1セット)の日数÷7で求められます。
この他にも、変形の対象となる期間の長さによっては、労基法でさらなる規制が課されています。
2-2. 変形労働時間制での残業代の計算方法
変形労働時間制でも、
です。
2-2-1. 残業時間
変形労働時間制でも、所定労働時間(就業規則などで決められた労働時間)を超えた時間が残業時間になります。
法定休日に働いた場合には、働いた全ての時間が残業時間になります。
2-2-2. 1時間当たりの基礎賃金の計算
1時間あたりの基礎賃金は、通常の勤務体系の場合と同様に計算します。(1-2.をご覧ください。)
2-2-3. 残業代の割増率
法定労働時間外の残業は、割増率が1.25倍(深夜労働でもある場合は1.5倍)になります。
法定労働時間外の残業は、以下のいずれかに該当する残業です。
| 1日について、①所定労働時間が8時間を超える場合は所定労働時間を超えた部分の残業で、②そうでない場合は8時間を超えた部分の残業 |
| 1週間について、①所定労働時間が40時間を超える場合は所定労働時間を超えた部分の残業で、②そうでない場合は40時間を超えた部分の残業 |
| 変形の対象となる1セットの期間について、40時間×その期間の日数÷7で求められる法定労働時間の総枠を超えた部分の残業 |
中小企業ではない大企業においては、1か月あたりの法定労働時間を60時間以上超える部分の残業については、割増率が1.5倍(深夜労働でもある場合は1.75倍)になります。
他方、法定労働時間外の残業には該当しないものの、所定労働時間を超えた部分の残業、すなわち法定労働時間内の残業については、割増率を掛けることはありません。その部分の時間に1時間あたりの基礎賃金を掛けた金額が、そのまま残業代の金額になります。ただし、深夜労働でもある場合は、割増率1.25倍を掛けた金額になります。
1時間あたりの基礎賃金が1500円で、土日休みの週休2日、変形の対象となる期間は1か月ごととされている人を例にとって考えてみます。
1か月が28日間となる日曜始まりの月に、所定労働時間が
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 10時間 | 8時間 |
| 2週目 | 6時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 6時間 |
| 3週目 | 8時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 7時間 |
| 4週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 6時間 |
の合計158時間で、実際の労働時間が
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
| 1週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 10時間 | 8時間 |
| 2週目 | 6時間 | 8時間 | 8時間 | 9時間 | 7時間 |
| 3週目 | 8時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 8時間 |
| 4週目 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 |
だったとします。
この場合、法定労働時間内の残業は、2週目金曜日の1時間と4週目金曜日の1時間の合計2時間となります。
他方、2週目木曜日の1時間(1日あたり8時間を超えている)、3週目金曜日の1時間(1週あたり40時間を超えている)と4週目金曜日の1時間(法定労働時間の総枠160時間を超えている)の合計3時間は、法定労働時間外の残業になります。
したがって、この場合、
1500円×2時間=3000円(法定労働時間内の残業)
1500円×3時間×1.25=5625円(法定労働時間外の残業)
→3000円+5625円=8625円(合計)
の残業代が発生することとなります。
法定休日に働いた時間は、割増率が1.35倍(深夜労働でもある場合は1.6倍)になります。
3.フレックスタイム制の場合
最後に、フレックスタイム制の場合について説明します。
3-1. フレックスタイム制とは
「フレックスタイム制」は、労働者自身が出退勤の時刻を決める制度です。
フレックスタイム制では、出退勤の時刻を労働者が決めることから残業代は発生しないと思われがちですが、実際はそうとは限らず、残業代が発生することもあります。
フレックスタイム制では、就業規則などで、「清算期間」と「総労働時間」が決まっています。
「清算期間(せいさんきかん)」は労働時間を計算するための1セットの期間です。例えば、1か月単位を清算期間として定めると、1か月ごとに労働時間が計算されることになります。
「総労働時間(そうろうじどうかん)」は、清算期間中に何時間働くかという労働時間数です。
総労働時間には上限があり、「法定労働時間(ほうていろうどうじかん)の総枠(そうわく)」を超えてはなりません。法定労働時間の総枠は、原則として40時間×清算期間の日数÷7で求められます。清算期間が31日間の場合は177.1時間、30日間の場合は171.4時間、29日間の場合は165.7時間、28日間の場合は160時間となります。
フレックスタイム制でも、「総労働時間」を超えて働いた場合には、残業代が発生します。
3-2. フレックスタイム制での残業代の計算方法
フレックスタイム制でも、
です。
3-2-1. 残業時間
フレックスタイム制では、「総労働時間」を超えて働いた時間及び(清算期間が1か月を超える場合には)1か月の労働時間につき週平均50時間を超えて働いた時間が、残業時間になります。
法定休日に働いた場合には、通常は総労働時間とは別枠で、働いた全ての時間が残業時間になります。
3-2-2. 1時間あたりの基礎賃金の計算
1時間あたりの基礎賃金は、通常の勤務体系の場合と同様に計算します。(1-2.をご覧ください。)
3-2-3. 残業代の割増率
法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を超える部分については、割増率を掛けることはありません。その部分の時間に1時間あたりの基礎賃金を掛けた金額が、そのまま残業代の金額になります。ただし、深夜労働でもある場合は、割増率1.25倍を掛けた金額になります。
法定労働時間の総枠を超える部分については、割増率が1.25倍(深夜労働でもある場合は1.5倍)になります。
また、中小企業ではない大企業においては、1か月あたりの法定労働時間を60時間以上超える部分の残業については、割増率が1.5倍(深夜労働でもある場合は1.75倍)になります。
1時間あたりの基礎賃金が1500円で、清算期間は1か月ごととされている人を例にとって考えてみます。
この人が、清算期間が28日間、清算期間中の総労働時間が150時間となる月に、165時間働いたとします。
この場合、法定労働時間の総枠は160時間となります。したがって、法定労働時間の総枠の範囲内で総労働時間を超える部分は10時間、法定労働時間の総枠を超える部分は5時間となります。
したがって、この場合、
1500円×10時間=1万5000円(法定労働時間の総枠内の残業)
1500円×5時間×1.25=9375円(法定労働時間の総枠を超える残業)
→1万5000円+9375円=2万4375円(合計)
の残業代が発生することとなります。
法定休日に働いた時間は、割増率が1.35倍(深夜労働でもある場合は1.6倍)になります。
なお、フレックスタイム制で、総労働時間の範囲内の労働であっても、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働した場合には、別途賃金が割増されます。
この割増の金額は、深夜労働した時間に1時間あたりの基礎賃金を掛け、さらに0.25を掛けた金額になります。
(2020年4月21日更新)
まとめ
ご覧のとおり、残業代は基本的な理屈を理解すれば自分で計算することも可能ですが、自分で計算するのは少し気が重いという方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時は弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として残業代を正しく計算し会社との交渉や書類の作成などを全て行ってくれるので自分で対応する必要はありませんし、自分で請求する場合よりも残業代を払ってもらえる確率も払ってもらえる金額もぐんと上がります。
ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功/不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が通るか分からない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。
そんな方におすすめなのが『アテラ 残業代』です。
①『アテラ 残業代』では、弁護士の着手金を立替えてくれるので、お手元から現金を出さずに、弁護士に着手金を払って依頼することができます。
②さらに、『アテラ 残業代』を利用すると、敗訴した場合や会社からお金を回収できなかった場合には、立替えてもらった着手金を実質返済する必要がないので、リスク0で残業代請求を行うことができます。
残業代請求をするときのリスクは、最初の着手金を支払うことで敗訴したときに収支がマイナスになってしまうことですが、『アテラ 残業代』を利用することでそのリスクがなくなります。
着手金にお困りの方、残業代請求のリスクをゼロにしたい方は、ぜひ『アテラ 残業代』をご利用ください。
なお、着手金支払いの負担・リスクではなく、どの弁護士に頼むかでお悩みの方は、ぜひ株式会社日本リーガルネットワークが運営するWebサイト『残業代・解雇弁護士サーチ』の弁護士検索機能をご利用ください。
